
その先の親孝行2025.08.18供養のアイデア Vol.4|オンライン・データで故人を偲ぶ その方法と生前に備えておきたいこと
誰もがSNSを活用している現代社会。離れて暮らす家族とのやり取りや近況報告、写真の共有など、さまざまな用途で使っている人も多いでしょう。一方、故人のSNSアカウントや、遺品整理で出てきたアルバムなどが放置されることも……。遺族の多くは「故人のSNSアカウントの削除やスマホを解約したいが、定期的に見返したい」「思い出のつまったアルバムは残したい」などの気持ちから、削除や処分に踏み切れないケースが多いそうです。そこで今回は、故人の写真やSNSなど、思い出をデジタル整理するためのノウハウをご紹介します。
紙の写真はデータで保存、いつでも気軽に見返して故人を偲ぶ

昭和世代の人は、イベントごとに写真を残している人が多いかもしれません。年代別でアルバムに整理していた人もいるでしょう。写真を見ながら「こんな時代もあったな」などと振り返るのは楽しいですよね。でも、写真やアルバムが大量にある場合、そのまま保管しておくと場所を取りますし、経年劣化で色褪せたり、紛失してしまったりすることも。箱などに入れたまま写真が重なった状態だと、表面がくっついて剥がれなくなる場合もあります。
そんなときは、取っておきたい写真をデータ化するのがおすすめです。最も簡単なのは、スキャナーでパソコンに取り込み、HDDやUSBメモリなどデータ保存用の端末に移す方法。スキャナーがなくても、スマートフォンでも遠近や角度の補正などをしてくれるフォトスキャンMicrosoft Lens などのアプリもあります。
スマホやスキャナーの操作に自信がない方は、専門の業者に依頼してもいいでしょう。写真アルバムをDVDやBlu-rayにデータ保存してTVで観られる 「アルバムそのままDVD(【カメラのキタムラ】アルバムそのままDVD(お店注文)|写真プリント・ネットプリントサービス)」などのサービスもあり、アルバムの雰囲気を残したまま、デジタル化する方法もあります。
データにした後、アルバムや紙の写真は燃えるゴミに出せば処分できます。でも、ゴミとしての処分に抵抗があるときは、神社やお寺でお焚き上げ供養する方法もあります。
故人が写っている写真や、思い出が詰まったアルバムを手放すには勇気が必要かもしれません。でも、写真をデータにすることで、管理が簡単になり、引っ越しなどの際も荷物が減らせます。携帯しやすくなるため、帰省や親戚との集まり、故人の友人・知人と会ったときなど、気軽に写真を見ながら思い出話ができます。
DVDやBlu-rayに落とし込んだ写真を自宅のTVで流しながら、故人との思い出を家族で語らうのもいいですよね。大切なのは、写真そのものより故人の思い出を家族や親しい人と共有し、いつまでも忘れずに偲ぶことです。その手段の一つとして、写真のデータ化を検討してみてはいかがでしょうか。
故人が残したデジタルデータの管理はどうする?
近年では、老若男女問わず、スマホやパソコンなどに写真や文書を保存することが一般的。もし、故人のスマホに思い出の写真がたくさん残されていた場合、スマホをどうするか悩みますよね。
スマホやパソコンの写真や文書などのデータを残しておきたいときは、遺族のクラウドストレージ、HDD、USBメモリなどに移行するとよいでしょう。
故人のデジタルデータを整理するには、スマホやパソコンのロック解除やデータにアクセスするためのパスワードが必要です。故人のメモなどが残っていればいいのですが、そうでない場合、パスワードはスマホのキャリア会社でも解除できません。こうしたときは、デジタル遺品整理業者にパスワードの解除を依頼する方法があります。
ただ、パスワードには非常に強力なセキュリティがかかっており、解除作業には困難を伴うため、費用には幅があります。相場は2万円~5万円とされていますが、ケースバイケースなのでデジタル遺品整理業者に相談して検討してみましょう。
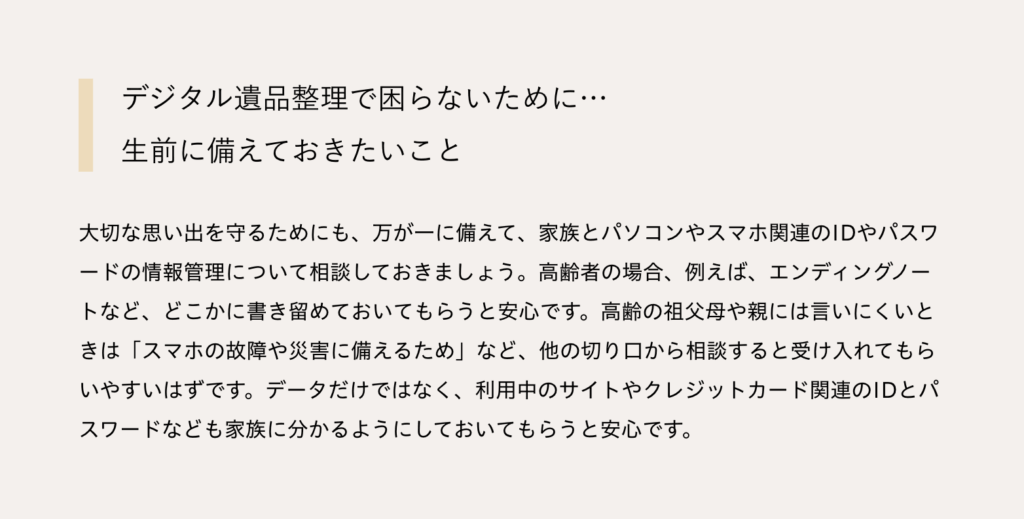
SNSの追悼アカウント

最近では、高齢のSNSユーザーも増えています。自身の日常や趣味に関する発信を行い、フォロワーとのコミュニケーションを楽しんでいる人もたくさんいます。自分では投稿しなくても、閲覧用アカウントを持っている人も少なくありません。
しかし、万が一の場合は遺族の判断でSNSのアカウントをどうするか決めなければなりません。フォロワーのためにしばらく残す、すぐに削除するなどいくつか選択肢があると思います。
幅広い年代の人が利用しているFacebookでは、ユーザーが「追悼アカウント」の管理人を指定できるようになっています。「追悼アカウント」とは、故人のSNSアカウントを特別な形で残すことができる仕組み。
Facebookの追悼アカウントは、ユーザーが亡くなった後、追悼アカウントに切り替えるための申請を行うと、ログインできなくなりますが過去の投稿は閲覧できます。また、管理人が一部の情報を更新できるため、連絡先を知らない故人の知り合いへの通知などに活用できます。
Facebook以外のSNSでは、XやLINEのユーザーも多いでしょう。これらに追悼アカウント機能はありませんが、遺族であればアカウント削除の申請ができます。ただ、手間がかかるので、故人のIDとパスワードでログインして削除したほうが早いかもしれません。残しておきたいSNSの投稿は、削除する前に、スクリーンショットを活用してデータ化しておきましょう。
■追悼アカウントについてのまとめ
●Facebook
Facebookで追悼アカウント管理人を追加、変更、削除する | Facebookヘルプセンター
https://dendingnote.com/memorial-account-instagram/
●Facebook以外の各SNSの追悼アカウントの設定方法
https://d-endingnote.com/memorial-account-instagram/
●TikTok
2025年7月時点では特に追悼アカウントなどはなし
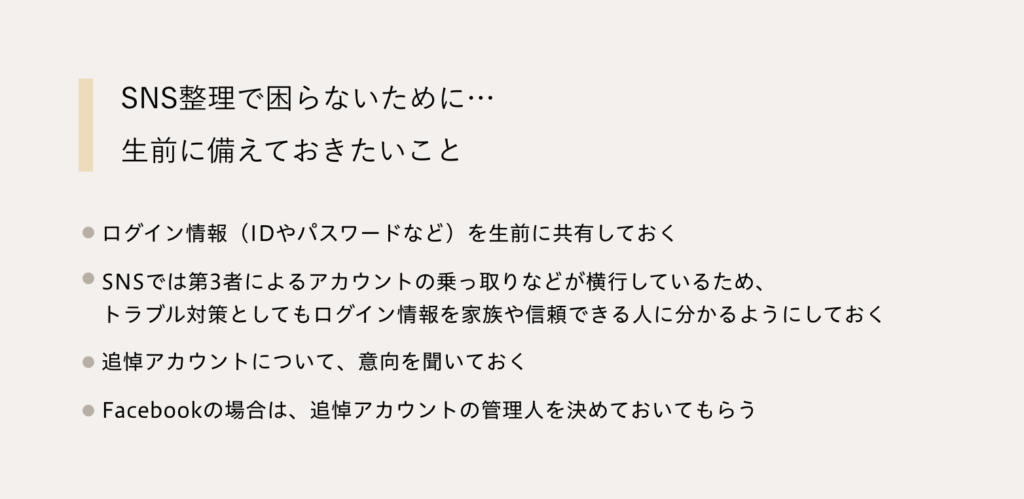
SNSの投稿には、故人の感情や本音がつづられている場合が多いです。Facebookの「友達」やフォロワーと、故人の投稿内容を共有し、ともに思い出を振り返るツール、記録としてアカウントを残しておくのもいいかもしれません。
まとめ:整理したアカウントやデータで故人を偲ぶ
大切な人と別れた後は、ふと、会いたくなったり話したりしたくなるものです。そんなときのためにも、故人との思い出はできるだけたくさん残しておきたいですよね。紙の写真では保管が大変ですが、データとして整理しておくと、思い出したときすぐに故人を偲ぶことができます。アルバムなどの写真データを離れて暮らす家族、故人が親しくしていた人と共有すれば、故人について語り合う機会が増えるかもしれません。SNSの追悼アカウントは、故人を偲ぶ場になるでしょう。残された人達で故人を想うことも、心のこもった供養のあり方の1つです。
